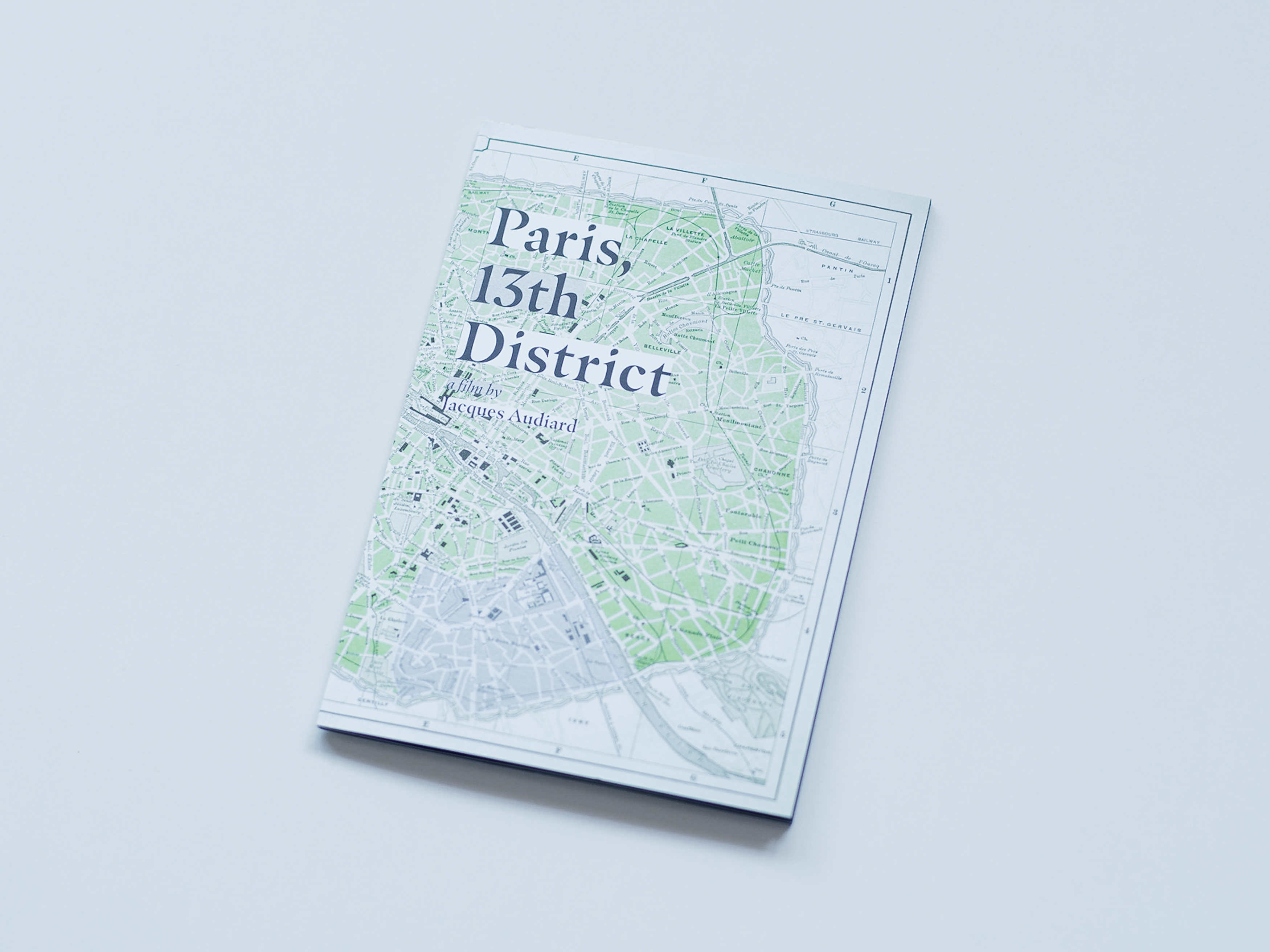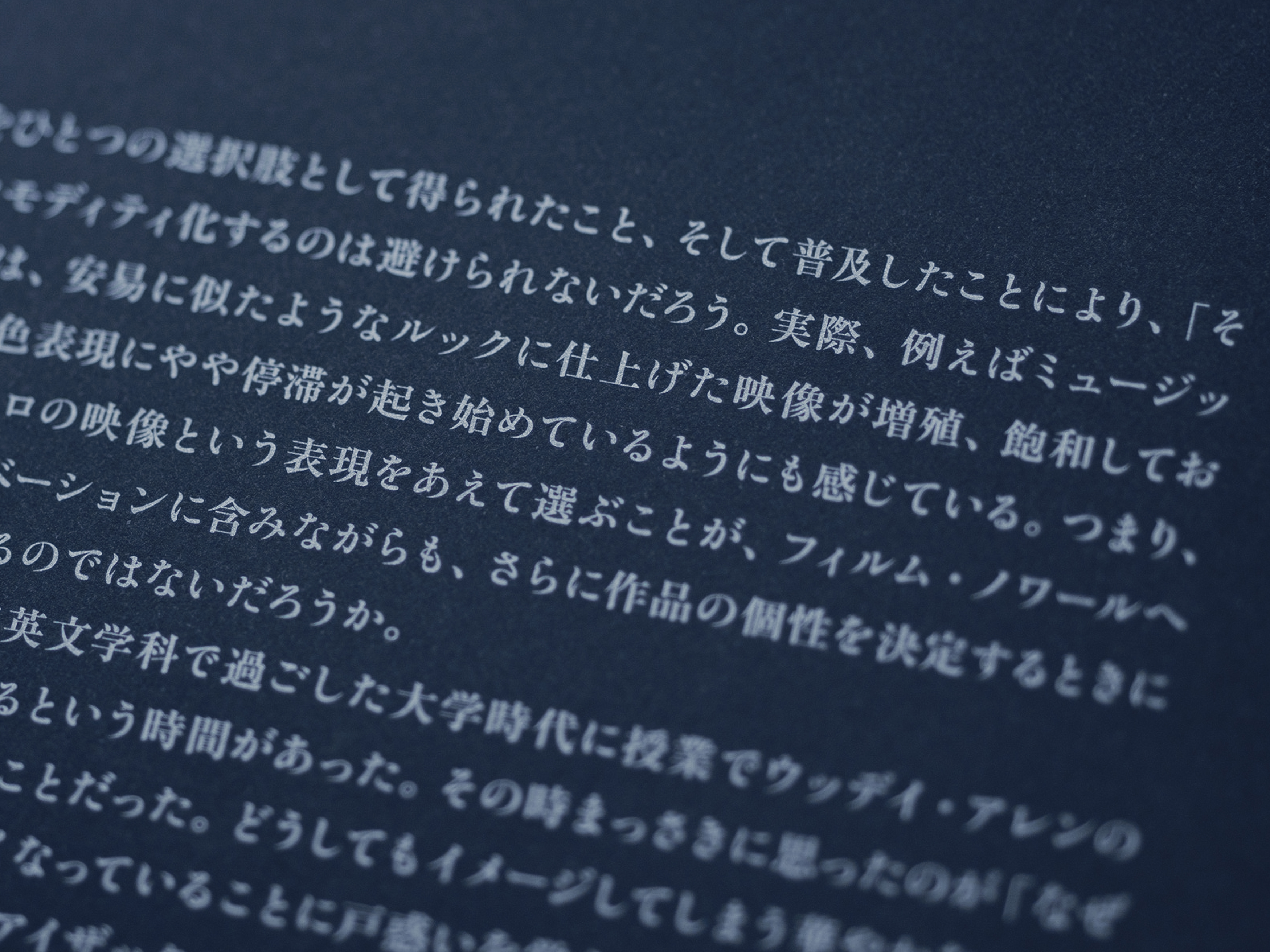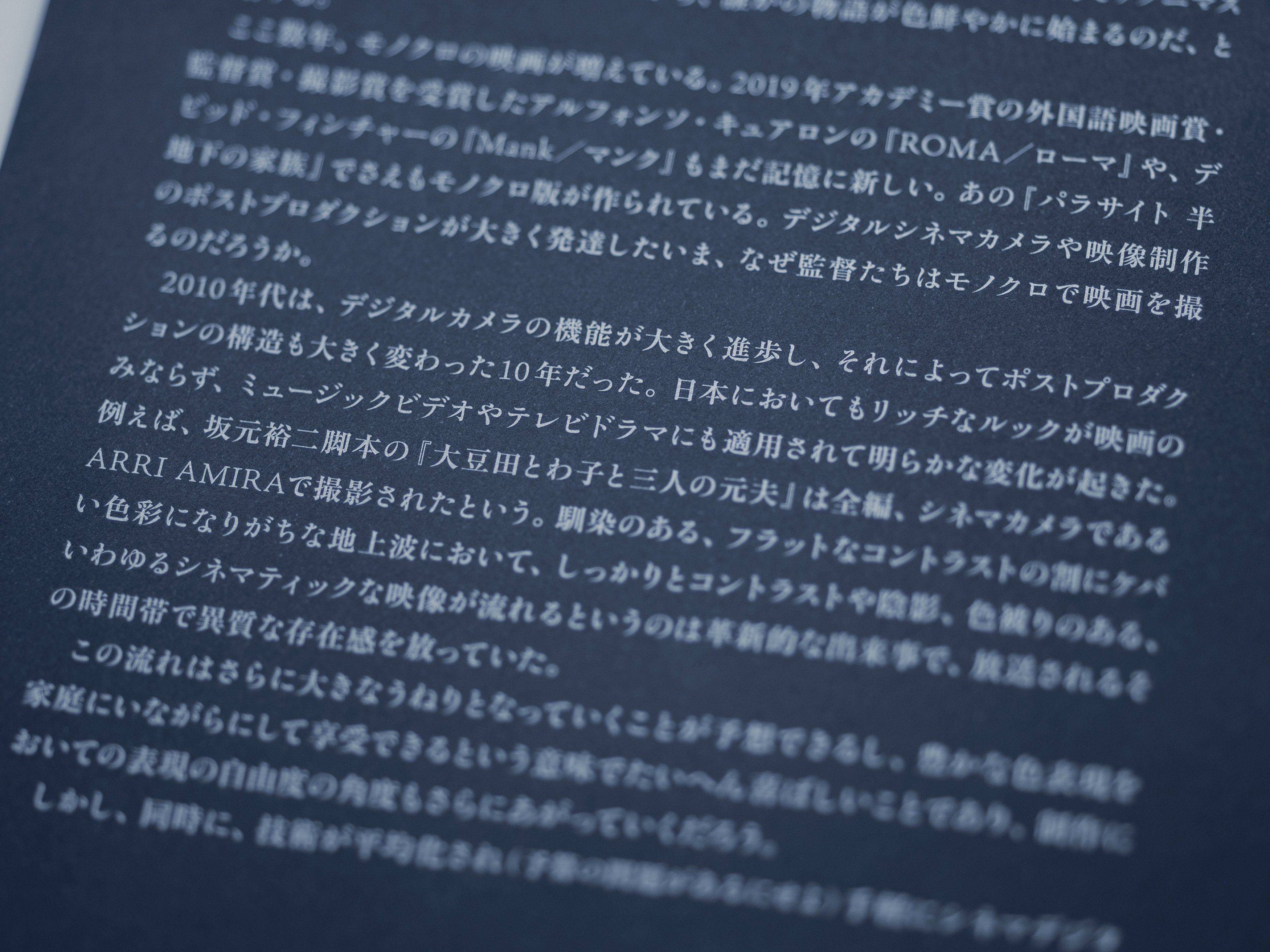モノクロだからこそ色鮮やかに輝く現代劇。
まずはオープニングから大胆な俯瞰のロングショット。目線は林立する無表情なビル群を舐めるようにパンしていく。カメラは街の片隅で生活する人々の姿を次々に覗き見る。そのワークはまるで飛ぶ鳥のようになめらかだ。微かな光が透ける煙が遠くの何かの工場から上がっている。その建築物のデザインのせいなのか、およそパリと知ってイメージする風景とは全く別の、もしかしたらシンガポールや台湾あたりのレジデンスだろうかと思わせる。だが、どうやらここはパリらしい。そして、この映画もやはりモノクロだ。色の情報が排除されることで、映像がより抽象的でアノニマスな印象を直感的に与えてくる。それから、誰かの物語が色鮮やかに始まるのだ、と理解する。
ここ数年、モノクロの映画が増えている。2019年アカデミー賞の外国語映画賞・監督賞・撮影賞を受賞したアルフォンソ・キュアロンの『ROMA/ローマ』や、デビッド・フィンチャーの『Mank/マンク』もまだ記憶に新しい。あの『パラサイト 半地下の家族』でさえもモノクロ版が作られている。デジタルシネマカメラや映像制作のポストプロダクションが大きく発達したいま、なぜ監督たちはモノクロで映画を撮るのだろうか。
2010年代は、デジタルカメラの機能が大きく進歩し、それによってプロダクションの構造も大きく変わった10年だった。日本においてもリッチなルックが映画のみならず、ミュージックビデオやテレビドラマにも適用されて明らかな変化が起きた。例えば、坂元裕二脚本の『大豆田とわ子と三人の元夫』は全編、シネマカメラであるARRI AMIRAで撮影されたという。馴染のある、フラットなコントラストの割にケバい色彩になりがちな地上波において、しっかりとコントラストや陰影、色被りのある、いわゆるシネマティックな映像が流れるというのは革新的な出来事で、放送されるその時間帯で異質な存在感を放っていた。
この流れはさらに大きなうねりとなっていくことが予想できるし、豊かな色表現を家庭にいながらにして享受できるという意味でたいへん喜ばしいことであり、制作においての表現の自由度の角度もさらにあがっていくだろう。
しかし、同時に、技術が平均化され(予算の問題があるにせよ)手軽にシネマデジタルカメラの導入をひとつの選択肢として得られたこと、そして普及したことにより、「そういうルック」がコモディティ化するのは避けられないだろう。実際、安易に似たようなルックに仕上げた映像が増殖、飽和したことで、現代に観られる色表現にやや停滞が起き始めているようにも感じるのだ。つまり、その反動としてモノクロの映像という表現をあえて選ぶことが、フィルム・ノワールへの憧れや影響をモチベーションに含みながらも、さらに作品の個性を決定するときに強い力を持ち始めているのではないだろうか。
話は変わるが、かつて英文学科で過ごした大学時代に授業でウッデイ・アレンの『マンハッタン』を鑑賞するという時間があった。その時まっさきに思ったのが「なぜモノクロなのだろう」ということだった。どうしてもイメージしてしまう華やかなニューヨークの暮らしから色がなくなっていることに戸惑いを覚えたものだ。しかし、その内容といえば、アレン演じるアイザックの冴えない(そして、いつも通り卑屈な)恋愛事情だ。淡々と風通しよく進むテンポとモノクロの映像が妙にマッチするのだと、20年以上が過ぎた今なら理解できる。改めて、アイザックとダイアン・キートン演じるメリーがクイーンズボローブリッジの袂で迎える夜明けのシーンはガーシュインのスコアと相まって、とても色鮮やかに見えた。
さて、ここで本映画と『マンハッタン』の共通点が浮き上がってくる。モノクロである点はもちろん、複数の登場人物が交差しながら恋愛模様を描いていくところだ。スマホやSNS、ルームシェアなどをそのトリガーとして取り入れているところは今のリアルだが、キャラクターの背景を深いところまで描き切らずテンポよく軽やかに見せるところは現代版『マンハッタン』のように思えたのだ。そして、さまざまな人種が交わる様がモノクロの映像になることで色彩的に対等に描かれているのに対して、キャラクターの個性やその関係性、それを取り囲む風景はむしろどんどん色鮮やかになっていくのだ。その意味で、ここ数年起きているモノクロ回帰のムーブメントとは異なるモチベーションを『パリ13区』に感じたのだった。
余談だが、本作の撮影監督であるポール・ギロームが同じく担当した、あのカニエ・ウェストの新作『Heaven and Hell』のミュージックビデオがパリで撮影され、しかもモノクロで作られているというのは実に興味深い繋がりだろう。
ジャック・オディアール監督の映画『パリ13区』パンフレットにコラムを寄稿いたしました。デザインは大島依提亜さんです。本コラムでは、2010年代以降、デジタルシネマカメラやカラーグレーディングの技術が発達したことで、クオリティの高いモノクロ映像の映画が同時多発した状況において、本映画がどのような立ち位置になるのかを映像制作にも携わる写真家の立場から考察しました。ライターでもなく映画をつくっているわけでもないのにも関わらずパンフレットの貴重なページをご用意してくださった配給のロングライドさんに感謝いたします。ありがとうございました。
応援コメント
“まったく新しいパリのイメージの中で、モノクロで映し出された群像が色鮮やかに輝きはじめたとき、同じような胸の高鳴りを覚えてなんだか走り出したくなりました。 濱田英明”
映画『パリ13区』公式サイト
https://longride.jp/paris13/