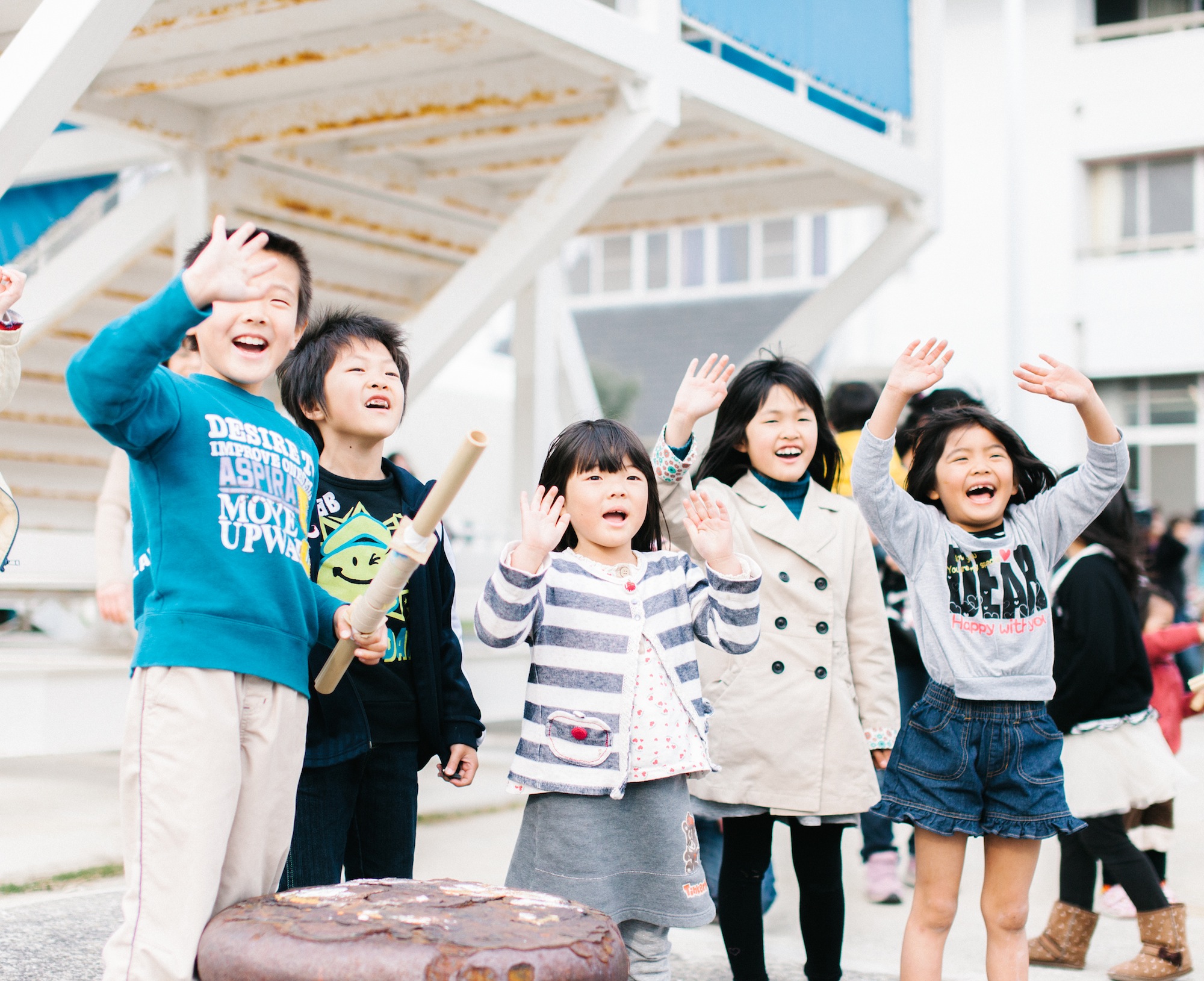「私たちと一緒に小豆島へ来てほしい!」その言葉がすべてのはじまりだった。
きっかけは「醤の郷+坂手港プロジェクト」を企画する原田祐馬くんと多田智美さんに出会ったことだった。大阪のとあるイベントの打ち上げで彼らと偶然一緒になったのだ。僕が自己紹介がてらに持っていた作品集を見るなり、彼らはその場で僕を小豆島に誘った。それが冒頭の言葉だった。
彼らの熱意に打たれた僕は訳のわからぬまま、その場で「行きます!」と応えてしまった。その時点で、瀬戸内国際芸術祭2013の開幕まで約一ヶ月という急展開な状況だったけれど、すぐに引き受けたのは、不安よりも、これはきっと楽しいことになるぞ、というわくわくした気持ちのほうが大きかったからだと思う。
とはいえ、僕自身が小豆島という場所やそこで暮らす人たちとこれほどまでにかかわりを持つことになろうとは、そのときはまったく想像していなかった。
僕の小豆島に おける主な仕事は Creator in Residence「ei」(以下、CiR)の記録撮影だった。さまざまな分野で活躍するアーティストやクリエイターたちが坂手を中心に、十日間という限られた期間のなかで滞在制作する様子や、島の人たちとかかわっていく過程、また、それに付随して計画的・偶発的に発生する出来事一つひとつを取りこぼすことなく写真で残していくことだった。
春会期の頃は、クリエイターもスタッフも何をするにも手探りのように見えたし、ましてや僕なんかは出会う人たち全員と「はじめまして」のところからスタートしなければならなかった。
僕が島の人たちと出会うときはだいたいCiRクリエイターの活動を通してだった。例えば、彼らがスタジオを出てまちをリサーチするときや、島の人たちを招待して懇親会を開くときだ。彼らの活動を追っていた僕はその都度いろんな人たちに出会うことができた。
ただ、僕自身が何者であるかを一対一で話せる機会というのはあまりなかったように思う。なぜなら、僕は芸術祭の招待作家でもなければ運営スタッフでもなかったからだ。それに、最初は僕もその「近すぎない距離感」を意識していたと思う。すべてを記録するうえで客観的にいられるかどうかはとても重要なことだったし、ゆっくり挨拶する間もなくいろんな物事が同時に進んでいくので、その瞬間を収めていくのに必死だった。
CiR第三期の「飯田将平と海辺の人々」を追っているときのことだった。僕は、坂手に住む西濱さんという年配の漁師に出会うことになる。ある日、飯田くんたちが西濱さんに会いに行くというので同行した。いつものように僕が写真を撮っていたら「影が消えるからやめろぉ!」と西濱さんに言われてしまった。少し恥ずかしそうな表情をされていたのを覚えている。まずいなあ、怒られた、と思った僕はそれでも「すみません! 撮らせてください!」と謝りながらこっそり撮り続けた。
夏会期の頃には、なぜか西濱さんは「この人に話を聞けばヒントがもらえるおじいさん的存在」になっていたので、CiRのプログラムで滞在するクリエイターが来島するごとに僕も会う機会が多くなり、おのずと西濱さんを撮る回数も増えていった。いつも視界の端っこでパシパシ写真を撮っている僕を気にしているようだった。「あいつまた撮ってるな、もうやめい」という具合に。
CiR第四期、NOSIGNERの活動は、坂手のまちを見下ろす荒神社(=通称、荒神さん)やお寺のおそうじプロジェクトだった。荒神さんは西濱さんの家の目の前にあって、管理も西濱さんがおひとりでされていた。ある日、西濱さんの案内で小豆島の第一霊場である洞雲山にみんなで行くことになった。僕は移動時はいつもひとりだったのだけれど、このときは西濱さんとバイクでツーリングとばかりに一緒に移動した。それから、西濱さんに一対一でいろんな話をしてもらった。ご家族のこと、昔、山伏だったこと、荒神さんのことも。
NOSIGNERの滞在期間が終了し、僕も小豆島以外の仕事のためにしばらく島にいない時期があって、西濱さんと会う機会はずいぶんと減ってしまっていた。そんなときに、坂手の町でばったりと西濱さんに再会することがあった。僕を見つけると「おーい! お前どこ行っとったんや。お前が来るん待ってたんやぞ!」と大きく手を振ってくれた。西濱さんは驚く僕を坂の上にある家まで連れて行った。玄関先で待っていると、西濱さんは大きな写真の入った額を持ち出してきて僕に見せた。それはどこかで見覚えのある「夏至観音」の写真だった。でも、なぜ西濱さんがこれを持っているのだろうか?
「夏至観音」とは、夏至の晴れた日の数分だけ、洞雲山の荘厳な岩壁にまるで観音さまのような姿が浮かび上がるという光の現象である。僕は実際にこの現象を見たことはなかったけれど、「夏至観音」の古い観光案内ポスターが島のいろんなところに貼ってあるので見覚えがあった。驚くべきことに、そのポスターに使われている原版写真は西濱さんの撮影によるものだったのだ。西濱さんは、そのことを伝えるために僕がまた島に来るのを待ってくれていた。そして、西濱さんは僕に、「この原版写真を複写して小さくプリントしたものをお守りとしてみんなに配ってほしい」と頼んだ。
僕は、それまで、もしかしたら西濱さんは僕が仕事として写真を撮っているということを知らないのかもしれないと思っていた。けれど、僕だけにこの写真を見せ、一枚しかないプリントを綺麗な状態で未来に残す仕事を託してくれた。そのことは、僕が何者であるかを理解してくれていることを意味していた。それまでの僕にとって小豆島にいる理由はあくまでも仕事だった。でも、この日を境に、僕の島に対する考え方や距離感が変わった。そうやって、自分に会いたいと思ってくれる人がここにいることで、素直にまた来たいと思えるようになった。そして、ここにいる人たちに自分のことをもっと知ってもらいたいとも思うようになった。
僕の仕事は写真を撮ることだ。そもそも写真には「被写体とのかかわり」が必ず内包されている。小豆島に行く前からそのことはわかっていたけれど、絶対的な確信を得られたのはこの仕事のおかげだと思う。夏会期の最後、島を離れる日に僕は、まるで写真の行商(実際は無料だったけれど)のように、それまで撮らせてもらった写真のプリントをまちの人たちに配り歩いた。もちろん最初に訪れたのは西濱さんのお家だった。あれほど「影が消える」と怒っていた西濱さんは照れながらも写真をもらってくれた。そこに写る西濱さんの表情はおだやかで、微笑みながらまっすぐカメラ(僕)を見つめている。こうやって、人としての関係を育み、写真を撮らせてもらい、形のあるものとして手渡し、残す。僕は写真が持つこの一連の流れが大好きなのだと思う。
僕がこうやって語ることのできる小豆島のストーリーは、実はほかにもいくつかある。もっと言えば、島を訪れていた人たち全員が同じように誰かと何らかのかかわりを持っていたはずだ。それぞれが島に帰ってくる、ここに居続ける理由を持っている。そうやって点在する関係性の質量や熱量は簡単にはかることはできないし、まだまだこれから続いていくものだと思う。
僕は、ただの記録係でありながら、結果的にそれ以上のところへ踏み込んだ。かといって、通りがかりの旅人でもなく、島の住人でもなかった。だからこそ、芸術祭というある種の魔法が解けたとき、試されるのは自分の職能だけではなく、人としての在り方だということにも気づけた。そこにクリエイターかスタッフか、そのどちらでもないか、というような肩書きはもう存在しないし関係がないように思う。この小豆島で豊かなつながりの種を蒔けたことを幸せに思うと同時に、今は、それを未来に向けてどう育てていこうかと、とてもわくわくしているところだ。
–
–
本文は2014年に出版された『小豆島にみる日本の未来のつくり方』(誠文堂新光社刊)に寄稿したエッセイを加筆修正したものになります。