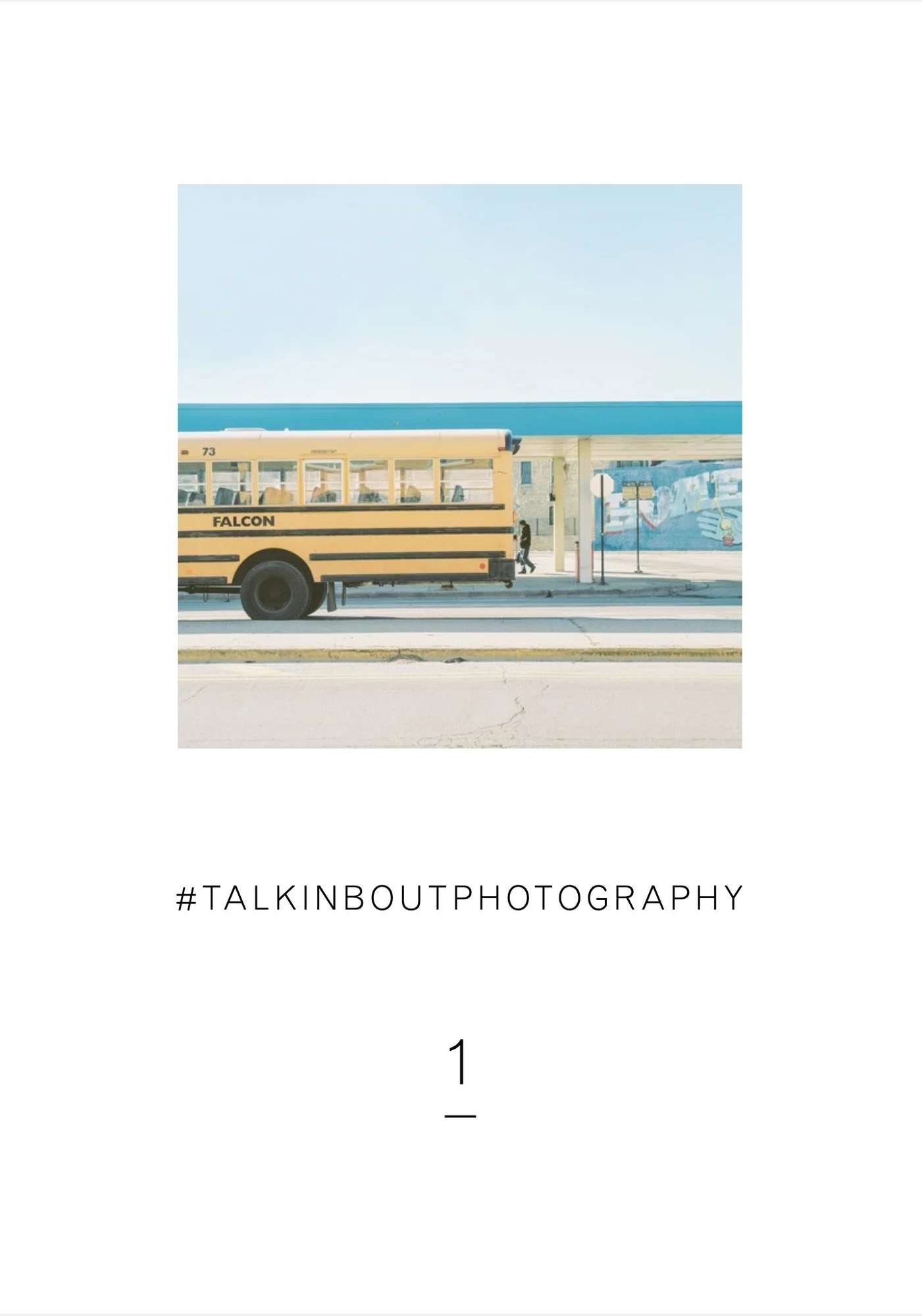このテキストは2016年4月、編集者の岡本仁さんと渋谷パブリッシングの企画によって、その後連続して開催されたトークイベントである『#TALKINBOUTPHOTOGRAPHY』を元に、第一弾としてつくられたZINEから抜粋したものを掲載しています。
岡本仁さん
https://www.instagram.com/manincafe/
#TALKINBOUTPHOTOGRAPHY 1
https://www.shibuyabooks.co.jp/information/2364/
以下、インタビュー。
–
岡本仁(以下O) 濱田くんは今もツイッターをやっていますか?
濱田英明(以下H) SNSは一通り全部やっています。
O:ぼくはもうツイッターもフェイスブックもやってないんですけど。たしかツイッターで、濱田くんがこの写真家はフォローすべきみたいなツイートを前にして、ングァンのアカウントのリンクを紹介していたことがあったんですよ。それでリンクをだどってみたら、すごく良くて、そこからぼくはングァンをフォローをしたんですよね。
H:そういうことだったんですね。
Nguan
https://www.instagram.com/_nguan_/
O:そうなんです。でもプロの写真家なのか、ただ写真の上手なインスタ好きな人なのか、どこの国の人なのか。調べればわかったんでしょうけれど、調べないタイプなので、何も知らないままフォローしていました。去年、鹿児島で濱田くんに会った時に、2人で前日のトークショーではあれが話したかった、これが話したかったみたいに、コーヒーを飲みなが反省会みたいになって、その時に濱田くんがングァンの写真集をくれて、実際に写真集とかまで出ている人だったんだとわかりました。それがちょうど、1号だけ復刊する『リラックス』で何かを書こうというタイミングだったので、もういま起きたことをそのまま書きましょうと思った。ぼくにとって何が面白かったかというと、写真家の写真をインスタで知る時代なんだよなっていう点です。それを皆に感じてほしいから、起きた順番をそのまま書いちゃって、彼から写真のデータをもらって、それをきっちり印刷して雑誌に載せようと思ったんです。それでングァン本人とメールのやりとりを始めたんだけど、英文で「You」と「I」だから男か女かもわからないし、最初にインスタであなたが男性か女性か、何歳か、どこの国に住んでいるかも知らなくてフォローしていたんだけど、その写真を『リラックス』で使わせてくれって書いたら、「何も知らないってすごく面白いね」っていう返事がきちゃったんですよ。そう言われちゃったらね、あらためて質問するのは野暮じゃないですか(笑)。じゃあ、知らないまんまでいいやってことで、いまだに知らないまんまなんですけどね。
H:そこまでいくと潔いですね。調べない(笑)
O:(笑)。じゃあ、そろそろ本題にはいりますけど、このングァンのちょっと前のフォロワー数がですね、35.1Kなんですよ。けっこう多いですよね。
H:もちろん多いと思います。
O:もちろん多いで言ったらさ、濱田くん、204Kとかでしょ今? 205K?
H:203Kですね。
O:203Kということは、20万3千人ですよね。これってすごく多いと思うんですよ。今すごく話題の奥山由之さんが11.5K。1万ちょっとですね。あと、高橋ヨーコちゃん。ぼくの仲の良い友達なんですけど、彼女で17Kくらい。1万7千人。その写真家の名前を見たり、作品自体を見たり、あるいは写真展を見たり、雑誌に載ってる写真を見たりする有名な写真家で、しかもインスタグラムをやっている人っていうのを、自分がフォローしている人を中心に面白いから数を調べてみました。だいたい数千人なんですよ。プロの写真家がインスタグラムをやっても、単純にKはつかないんだなっていうのがわかる。
H:単純にKはつかない(笑)。
O:具体的に名前出すとあれだから出さないけど、ちゃんと数は調べたました。それでね、面白いからついでだと思って、アメリカ人のプロフェッショナルなフォトグラファーも調べたんですよ。ぼくの好きな人ばっかりだけど。ジョエル・マイロウィッツが25.1Kです。2万5千人ね。それから、知らなかったら皆んまもぜひフォローしたら良いとおもうんですけど、スティーブン・ショア。彼が65.3Kです。6万5千人。あとはですね、エド・テンプルトン。ずっと年齢が若くなりますけど152K。15万人。さらに、ぼくあまり趣味じゃなんだけど、多分この人は絶対多いだろうと思ってテリー・リチャードソンも見てみました。1M。100万人ですよね。1ミリオン。もうKじゃない。あとは、この人が写真家かどうかってことは別にして、リチャード・プリンスが33.1K。ただしアカウントに鍵がかかっているんです。ぼく、申請を出してるんですけど、全然フォローさせてくれない(笑)
会場:(笑)
O:そりゃそうだよね。誰だこいつ? って話でしょう。申請なんか読まないだろうな。あとラリー・クラークが24K。さらについでだから、もっと大御所を調べたんですよ。アーヴィング・ペンと、リチャード・アヴェドン。そしたらですね、アーヴィング・ペンは3088。
H:これってご本人ではないですよね? 誰が運営されているんですか?
O:アーヴィング・ペンフォトグラフィーっていう、多分財団というか事務所がやるんですよね。もしかしたら公式じゃないかもしれない。リチャード・アヴェドンもそうです。リチャード・アヴェドンファンデーション。739。ということでですね、インタスタグラムの世界では、写真家の知名度とか実力とかとは違う、別の評価が完全にあると。ぼくはですね、濱田くんのことをやっぱりインスタグラムで知ったんですね。濱田くんの写真で、印刷されたものをはじめて見たのは『Kinfolk』ではなくて、学芸大学駅のですね、『フード&カンパニー』の、『フード&カンパニー』っていうグローサリーストアがあるんですけど、そこのオープンを知らせるハガキです。「あ、この写真めっちゃかわいい」と思って壁に貼っておいたんだけど、あとでそれが濱田くんの写真だということがわかった。だから結局、写真家、写真を撮っているプロの人を知るってことが、こんな順番で起こりうるんだっていうのがすごく面白くて、とにかくこのトークのシリーズは濱田くんと話さなきゃだめだと思った次第なんです。それでね、まずいちばん最初に訊きたいのは、濱田くんのインスタグラムは、なんであんなにフォロワーが多いのだろうということ。自分ではどう思っていますか?
H:そうですね、そんなにすぐにそういうことになったわけではもちろんなくて、色々な文脈があるんですけれども。もともとインスタをやる前からネットっていう場所が、ぼくにとってメインの活動、表現、発信する場所だったんですよね。というのも、ぼくは職業としての写真家になってから、まだ3年ちょっとなので、それ以前は写真を職業としていませんでした。その時期に、まだインスタ前夜ですよね、具体的には2009年くらいからなんですけれども、Flickrをはじめたんです。写真をデスクトップパソコンで見るのがメインの時代ですけれども、座ってパソコン開いて落ち着いて見るっていうのが、当たり前の時代でした。それで写真共有ができるFlickrっていう場所で、趣味として写真を発表していたら、ここは多分ポイントだと思うんですけれど、ネットには断りなく写真を世に紹介してくれる人がいるんですよね。Flickrをやってる時にはじめて、そういう文化に出会うというか。FlickrにもSNS的な要素があって、誰かがいいねしてくれると、勝手に広まっていくんです。それを目の当たりにしました。そのあと、フランスの「Fubiz」という、写真だったりデザインだったりカルチャーだったり、世界各国のクリエイティブの情報を紹介するようなポータルサイトみたいのがあって、こういう類のサイトに、これも何の連絡もないんですが(笑)、気づいたら載っていたっていう。例えばこれはアメリカかな。「My Modern Metropolice」ていうところに載ったりとか。あとは、ポーランドの「THIS IS PAPER」とか、自分の写真がデザイン系のところで紹介されるようになったんですよね。
O:何の連絡もなく?
H:何の連絡もない。載ったあとも何の連絡もない(笑)。ぼくはネットサーフィンとかしていて、自分の写真にたまたま出会うっていう。ツイッターなり見ている時に「あれ?」みたいな。自分でポストしていないのに、出てくる。そこでまず、お仕事で写真をされている方は、多分怒るんじゃないかなって思うんですよね、通常であれば。ネットで勝手に無料配布されたりしたら、それはすごく皆さん困りますよね。でも、誤解を恐れずに言うと、ネットではある意味それが本質だと思うんですが、写真なりなんなりをシェアした時点で、その人の手を離れて勝手に漂流していくものだと、ぼくは思えるようになったんですよね。あ、そうなのかと。最初は驚くんですが、ここで何か抗議したり、どうこうするものではないんだなっていうふうに。じゃあ、どんどんやってくださいっていうふうに、ぼくは考えるようになったんです。よく作家のホームページを見ると、「無断転載禁止」ってありますが、ぼくはそれを言ったことが一度もないんです。転載禁止はもちろん当たり前だとは思うんです。道徳的にいけないと思うんですが、ネットっていう場所においてそれってすごくナンセンスだなって思っている自分もいて。あまり大声では言えないんですけれども。こと自分の写真に関しては、それは大丈夫っていうスタンスでずっとやってきたんですよね。それで淡々と写真をシェアして、誰かが紹介してくれるっていう積み重ねで今に至ります。それをOKだよって思うか、困るって思うかっていう境目は、まず職業として写真をやっている方だったらぶち当たると思うんですよ。でも、自分は自然な流れで乗り越えられたっていうのが、すごい大きいかなっていうのはひとつあると思います。
O:ということは、例えばさっき例に出した、知名度の高い写真家の人がそれほどフォロワー数が多くないっていうのは、もしかしたらそこの考え方が作品至上主義っていうところから抜け出せていない、それを共有するっていう感覚を持てないからっていうことですかね。
H:それが、いま変わってきたんだと思うんですよ。
O:なるほど。
H:2009年当時っていうのは、多分そういう考え方を持った職業写真家の人はほとんどいなかったと思うんですよね。ぼくが職業としていなかったっていうのももちろん大きいんですけど、どうぞ自由にやってくださいっていうふうに公に言える人っていうのは、そんなにいなかったんじゃないかなというか。それがちょっと早かったっていうのは、ひとつまた大きいと思って、要するにインスタっていうのが生まれる前から(注:インスタグラムのサービス開始は2010年)、見ている人は写真をフラットな目線で純粋に楽しんで、その写真を撮ったのがそれを職業としている人かそうじゃない人かっていうのを、あんまり気にしていなかったと思うんですよね。究極。ネットでは、それが誰が撮ったものなのかを気にしない。その写真が良いかどうかっていう、すごいフラットな目線で、国境を越えて言葉を越えて、評価される場所だと思うんです。そこに飛び込めたのがちょっと早かったのかなっていうのは、実感としてはあります。
O:でもFlickrがきっかけになって、職業写真家になるわけですよね。その前は、やっぱり写真撮影そのものの訓練というか、技術的なことを学んだりするっていうことはやっていたんですか。
H:ぼくは学校にもスタジオにも行っていないし、師匠にもついていないので、独学になると思います。いわゆる写真のアカデミックな場所、もしくはプロフェッショナルな場所で技術なりなんなりを身につけたことは、まったく一度もなくて。変な話、ちょっとそこはコンプレックスでもあるんですけども。自分の良さっていうのは、そういうところにはないと思いながらも、仕事をしていく上では必ずそういう場面にぶち当たるというか。仕事の現場では、自分ができること、できないことっていうのがけっこう明確に影響するところがあるので。あと「東京の写真業界」とか「ファッション業界」であるとか、そういうコミュニティの輪の中に、自分は一切入っていないっていう。
O:それは入りたくないの? 入れないの?
H:うーん、入れてもらえない(笑)? どっちなんでしょうね。今ようやく、自分がそこに入りたい、入りたくないに関わらず、お仕事として入りつつあるのかなっていう実感はありますね。それまではまったく蚊帳の外か、存在自体が知られていないか、もしくは本当にいるのかっていう都市伝説になってるみたいな感じ(笑)。どこにいるんですかみたいな(笑)。ユニコーンのような感じと言われたことはありますね。本当に存在しているのか、この人は、みたいな。ぼくは東京に住んだ経験はなくて今も大阪在住なんですが、たぶん、一般的なプロセスの中に自分の出自がないので、業界の方に知られる機会がなかったんだと思います。
O:それが、この人は本当に存在していて、プロの写真家なんだっていうのがある程度知れ渡るきっかけっていうのはなんだったと、自分では思っていますか。
H:今お話した経緯にあるように、そもそも自分の写真家としてのアイデンティティの出自はインターネットにあって、かつ日本からではないんですよね。ぼくの写真を勝手に紹介してくたのは、ほぼ海外の人たちです。おそらく海外のほうがそういう土壌というか、文化があると思うんですよね。そこに柔軟な考え方があるというか。なので、写真家になりますっていう宣言をした後も、ぼくはしばらく実際に日本での知名度っていうのはなかったと思うんですよ。なので『Kinfolk』という雑誌で撮ったのを、日本の人が見て逆にぼくのことを知るっていう事態が起きた。どちらかというと業界の方の反応が多かった。むしろ写真を好きな、それをお仕事にされてない、業界に属していない方には、ずっと前から見ていただいていることは実感としてはあったんです。ただ、それが仕事につながるかつながらないかっていう意味で『Kinfolk』は、ひとつのターニングポイントだったなと。それはありますね。
O:そうですよね。ぼくは雑誌の編集を長くやってきたので、このページの写真を誰にとってもらうかっていうことを、常日頃考えるわけで、そういう時にやっぱり他の雑誌で見かけて面白いと思うとか、あるいはいわゆる営業でポートフォリオを持って来てくれた人の中から面白い人を見つけるという感じでした。この間、濱田くんに鹿児島で会った時に「営業したことないでしょ?」って聞いたら、やっぱりそうだった。でも、それ以上にぼくが今日びっくりしたのは、やっぱり写真学校を出ていて、でもデザインの仕事をしていて、それでいつかは写真家になれたらって思っていたのかなって想像していたんですけど、そうじゃなかったところ。
H:そこは、これもあまり大声では言えないんですけど。
O:じゃあ小さな声で。
H:小さい声で(笑)。本当のことなんですけど、これまで1度も写真家になりたいって思ったことがないんです。
O:出た(笑)!
H:本当にすいません。嘘って思われる方いると思うんですけど。
O:ぼく2人目です。写真家になろうと思ったことはないって言って、ちゃんと写真家になっている人に会うの。もう1人は常盤響さん。常盤くんは写真家じゃねえじゃんって思った人もいると思うんだけど、ぼくは彼のことを写真家だと思ってるんで。
H:ぼくは流れに乗っかってやっているうちに、なってしまったという感じです。今置かれているような状況になるとは、写真家としてフリーランスでやりますよなんて、一切思っていなかったです。その前はとある編集プロファクションでインハウスデザイナーとして所属していて、その会社を辞める前日くらいに写真家になろうと思ったんですよ。というか、もうそれしか選択肢が残っていないっていう、実はちょっとネガティブな部分もあったりするんですけど。その仕事を辞めたときに、自分は今何ができるんだって思ったときに、こんなにいっぱいネットで自分の写真を見てくれている人がいるのに、それだったらこれをやるのが今は一番だなっていうふうに思えた。本当に写真家を目指すなら、例えば18歳から学校に入って、卒業してスタジオに入って、誰か師匠についてデビューっていうプロセスが一般的だと思うんですが、ぼくは一切踏んでいない。ところが、お仕事をやっていくうえでは、フォロワーが多いからとかはあまり関係なかったりするんですよね。。当然なんですが、実際撮れるかどうかっていうところがすごく大事だし。ようやく今、なんとなくバランスがとれてきた気がします。3年やってようやく。たくさんの編集者の方やアートディレクターの方とお仕事させていただくうちに、自分のできることとやりたいことがようやく一致してきたかなっていう気はしています。
O:写真家になる前とか、なろうと思ったときに、たくさんの人が見てくれている、世界中のたくさんの人が見てくれているっていう自信が、ある程度あるっておっしゃってたと思うんですけれども、そういうものをですね、なんの前提もなしに見ている人と、例えば仕事をくれる人、あるいは写真を評価する人たちが見ているものっていうのは、違うと思いますか。
H:うーん、それも今変わってきている。過渡期かなと思うんです。ただぼくが写真をはじめて仕事にしようと思った時は、そうではなかったなと思います。そもそもSNSのような場所に、まだ業界の方たちがいなかったんですよね。もしかしたら、そういう場所で見つけて仕事を依頼するという発想もなかったかもしれません。今ようやくみんな積極的にSNSなんかをされていると思うんですが、そういう場所で見られることがなかったので、評価されようもないっていう部分もあったし、写真家になるためのきっちりとしたプロセスを踏んでいないっていうのはやっぱり、大きかったのかなと思って。ただ一方で、それは本質ではないと思っている自分もいるんですよ。そういうプロセスを踏んでいない自分がコンプレックスでもありながら、じゃあプロセスを踏んでいないと評価されないのかっていうところには、すごく疑問はありますね。要するに、良い写真であれば評価されるべきだし、そこに肩書きであれ、経歴であり、実績っていうのは、本当は本質ではないとは思いたい。
O:そうですね。本質ではないかもしれないし、じゃあその写真を評価して自分の仕事を頼もうとする人が、自分の目で見ているかどうかもちょっと怪しい部分もある。さっき言ったみたいに、『Kinfolk』が起用したカメラマンがなんと大阪にいた、みたいな。で、いいじゃんって言う。でもそれは『Kinfolk』がいいのか、濱田くんの写真がいいのか、わからないじゃないですか。
H:そういう文脈になってしまうとわからないですね。
O:ですよね。だから、じゃあ評価する人は何を見ているんだって話になる。ぼくは『BRUTUS』でファッション担当だった時期があって、ファッションフォトグラフっていうのをすごくたくさん撮る現場にいたんです。その前は『ELLE JAPON』にいたから、やっぱりファッションフォト。ファッション写真って、わりと誰が撮るかがすごい重要というか、絶対その時に旬な人がいるんですよね。今だと、例えば奥山由之さんに頼むっていうのは、ある種の、もちろん奥山さん自身に力が無ければそれをこなせないし、それができているわけだけど、今は「奥山くんに頼むのがいいんじゃない?」っていう動きというか流行っていうのがすごくあると思うんですよ。だから、そういうものとは別な評価軸がネットにあったっていうところは、濱田くんと他の写真家の人たちと、やっぱり出てきかたが違いますよね、やっぱりね。
H:それって、ングァンのことも象徴的だと思うのですが、結局、誰が撮っているかわからなくても写真が良かったら見る、フォローするっていう世界だと思うんですよね。感覚的に良いかどうかっていうところがすごく大切な場所で。フォロワーが流れるタイムラインのなかで、いかに「ん?」ってそこで目や指を止められるか。どんどん流れ去ってしまうなかで、「いいね」するかどうかまで持っていけるかっていうのは、結局、写真の力でしかなくて。『Kinfolk』で撮りましたっていうイメージはぜんぜん役に立たないんですよね。
O:ぼくはflickrもフェイスブックもツイッターもやらないから、濱田くんの写真はインスタでしか見ていないんですけれども、例えばインスタグラムにポストする写真と、実際に仕事をする時に撮る写真っていうのは、別なものなんですか。
H:基本的には同じです、全部。
O:ですよね。
H:平等です。
O:例えば、ここには自分の本来の写真が載せられないから、インスタグラムでは発表せずに告知だけにするっていうアカウントもすごく多い中で、なんか濱田くんのはそうじゃないように見えるんですけど。
H:そうですね、発表の仕方もできるだけ手を抜かないようにしています。例えば、雑誌のお仕事をしました。その雑誌をスキャンするだけなら簡単ですが、たとえば綺麗な光のなかで撮ったり、少し環境を変えるだけで、その写真自体に魅力がうまれる。ただお知らせしました、だけで終わらないようにしたい。そこはすごく考えますね。その写真自体がやっぱり良くないと、がんばったお仕事をお知らせしたくても、流れていっちゃうのかなっていう、そういうこだわりっていうのはすごくありましたね。というのも、インスタであろうがお仕事であろうが、平等にクオリティを高めたいという動機のひとつになったきっかけがあったんです。リスペクトしている大御所の写真家の方が、おそらくなんとなしにSNSにアップした、たぶん携帯とかで撮った写真だと思うんですが、それがあまり良くなかったんですよね。
O:問題発言(笑)!
H:これも大声では言えないですね(笑)。でも実際にそうだったんです。その方の作品は素晴らしいし、写真集やプリントで見てきたものは本当にすごいのに、なぜこの携帯の写真は? みたいな。もちろん大御所の方たちはすでにキャリアがあって、そこに力を入れる必要もないとは思うんです。でもぼくは、人の目に触れる時点で最低限のクオリティを担保しないといけないと思っているんです。というか、そうしたい。すごく実績があるのに、たった1枚シェアされて流れてきたのが、その日食べたお昼ご飯の、しかも画質も低い写真だったりとかっていうのは、ちょっと寂しいなって思う。いかに取るに足らない内容でも、その人らしさとか、その人の良さみたいなものが見える写真にしないといけないんじゃないかなと。だから、自分の出自がインターネットだったっていうのは、すごく大きいですね。それをぼくがサボったら、ダメだろうっていうことですよ。自戒の念っていか、そういうのもあったし。それがきっかけで、いまでも覚えているんですけど、写真家になったあとすぐ、2013年の頭くらいにパーっと意識が変わったんですよね。全部一緒にするっていう。
O:それは、フィルムで撮ったものも、全部一緒にするっていうことですよね。
H:そうです。フィルムで撮ろうが、iPhoneで撮ろうが、デジイチ(デジタル一眼カメラ)で撮ろうが、どんなカメラで撮っても、ぼくが撮ったんだというのが分かる写真を目指したいと思ったんです。カメラが違うとこんなに写真が違うんだってなるのが、すごく嫌だったんですよね。そこにもひとつ、最初に質問いただいたフォロワーが多いっていうことの理由はあるかもしれないですね。小さい画面のなかだけでいかに美しく見せるかっていう環境だと思うので、それをサボったら絶対みてくれる人は増えないんじゃないかって。
O:1度リングにのぼったんだから、そこのルールで最高目指せ、みたいなこと?
H:そうですね。具体的にルールがあるっていうより、みんなそういうぶうに見ていると思います。インスタントな場所だからこそ、シンプルに良いかどうかが重要というか。
H:例えばもっと別の評価軸、添えられてるテキストが面白いとか、撮ってるテーマが面白いとかだったりで変わると思うんですが、自分はそういうアイデアの部分じゃなくて、なんでもない風景だったり出会った人だったり、要するに日常使いの延長でいかに勝負するか、そういうところすごい考えるので。
O:なるほど。濱田くんのインスタグラムを見ていると、PENTAX、ペンタ6×7って、それ、6×7サイズだから、ペンタ6×7っていう名前なのかと思うんですけど、それで撮られたものが多い。意外とiPhoneはないですよね?
H:あるんですよ、それが。
O:ある!?
H:もちろん数で言うと少ないと思うんですけど、それで、今日ちょっと持ってきたんですけど。ここに富士山の画像が何枚かあるんで、どれで撮ってかっていうお話をちょっとしたいなっと思って。まずこれ。
O:おぉ。
H:これ。
O:はい。
H:そしてこれ。全部違うカメラで撮ってます。
O:マジで?
H:はい。カメラは何かと言うと、今言った、PENTAX 6×7というフィルムの中判カメラか、デジタル一眼レフカメラか、iPhoneか。
O:これ、どれがどれですかね。ちょっと皆さんに、手を挙げてもらいましょうか。
H:じゃあ、どれがiPhoneで撮ったものか、にしましょうか。
O:そうですね。じゃあどれがiPhoneで撮られた写真か、挙手してもらいたいと思います。じゃあ皆さんから見て、左上がiPhone、だと思う人。
会場:挙手
O:では次。右上がiPhoneだと思う方。
会場:挙手
O:ちょっと多いですかね。じゃあこの下のがiPhoneだと思う方。
会場:挙手
O:これと思う人は少ないですね。
H:そうですね。
O:さて、あ、ぼくですか。ぼくはね、これがiPhoneだと思う。
H:なんでそう思われました?
O:新幹線から撮ってる感じがした、
H:(笑)一応どれも新幹線から撮ってます。
O:あ、そうですか。
H:今、自分ではすんごい面白い結果が出たなと思ってます。
O:あ、ほんとに。はい、正解は。
(しばし沈黙)
H:一番少なかった、これがiPhoneです。
O:えぇぇぇ!!!
H:っていうことをずっとやってるんです。(笑)
O:なるほど。これは具体的にまざまざと見せつけられちゃいましたね。
H:いや、結果が一番手が挙がらなかったのがiPhoneの写真だったのは、自分でもちょっと新鮮でしたね。
O:なるほど。や、わかんないってことですよね。
H:もちろんあの、突き詰めて見ていけばわかるんですよ。そういう目でもってみれば。
O:はい。
H:でもいかにそこを、クオリティを揃えて、カメラによって使われていない人になれるかっていうのに、すごくこう、執念を燃やしているというか。
O:カメラによって使われてない人って、すごくいい言い方ですね。
H:カメラは、結局、道具でしかなくて、それをいかに自分が使って、何を撮るかっていうところが、写真家にとっての本領というか、アイデンティティかなと思ってて。もちろんそのカメラの使い方を突き詰めて、極めればそれは一個のアイデンティティなんですけれども、自分の場合はそうじゃないし、「この人、携帯で撮ったらこんな下手なんだ」って思われるのがすごく嫌なんですよね。自分の辿ってきた道を振り返った時に、そこはやっぱり手が抜けない。
– 中略 –
O:そうですね。では、濱田くんが写真のアウトプットのクオリティを揃えるっていうことは、すごく理解できたんですけど、例えば、インスタグラムにポストすることと、写真展を開くことと、写真集を作ることには、重さの違いはありますか?
H:うーん、バーチャルとリアルって言葉があると思うんですけど、今の話をそれに置き換えた時に、そこは自分の中で分断されてないんですよね。言葉で分けた時に離れると思うんですけど、そこはこう、限りなくグラデーションというか、繋がってる行為だと思っていて、自分の中ではそれは当たり前になってるんですよね。なので、ぼくは写真集も出すし、写真展もするし、インスタもやってるけど、「価値」っていう意味では平等というか。
O:なるほど。
H:分断されてない。インスタでは、ある意味では写真集的な編集がなされた見せ方もしてるつもりだし、一つのギャラリーとしても成立してるのかなとも思うんですよね。で、そこで感じたこととか、見せ方とかっていうのを、本なり写真展にフィードバックすることもあるし。あ、そうそう、去年仕事で、鳥取県をずっと撮ってたんですけど、シンプルに鳥取の風景を撮る仕事で、で、それは全部PENTAX 6×7っていう長方形のフォーマットのやつで撮ったんです。でも展示するときに全部、正方形、スクエアにトリミングし直したんです。なんでかっていうと、出来上がった写真をまずインスタにポストしてたっていうのがあって、そこで正方形にトリミングしたものをシェアしてみんなに見てもらって、それから写真展に来てもらおうと思ったのと、あと岡本さんがやっぱり「スクエアだよ・・・」って言ってて。
会場:(笑)
O:(笑)。その頃って一番うるさく言ってた時ですね。
H:正方形にして岡本さんに見て頂こうかなっていう。それでスクエアにしたんですよ。そういうちょっとあざとさもある。
会場:(笑)
H:でも、たまに「なんでこれ67で撮ってるのにスクエアにするんですか」っていう質問をいただくんですね、そこにこだわって撮ってるんじゃないんですかって言われるんですけど。ツッコミをいただくんです。
O:でしょうね
H:なんて言うのかな、自分がたどってきた道がデザイナーだったので、実は、6×7でないといけないってこだわりはあんまりなかったりするんですよね。撮る時に、6×7で構図を作ったけど、そのあともう一回スクエアにトリミングし直す時の気持ち良さみたいなのもあるんですよね。そういうのってデザイナー目線かなとも思ってて。どこで切るか、例えば、空を残すか残さないかで、その写真の意味ってすごい変わると思うんです。
O:はい。
H:撮った日の感情と、トリミングして、アウトプットする時の感情がまた違ったりして、すごい新鮮です、自分では。違う意味が生まれるし、違う編集が成されるなあと思ってて。そういうのがぼくは好きなんですよね。
– 中略 –
O:では、撮ろうと思う対象との距離っていうのが、その写真家の性格を決めるというか、その写真の性格決めるってなんとなく思ってるんですけど、濱田君が、好きな距離感ってありますか。
H:えーと、自分は多分、近寄りすぎないはずなんです。ただ遠くもないっていうのを、意識はしてると思います。踏み込み過ぎないし、でも、他人ではない距離感。ちょっと言いにくいですけど。そこは、最初に言った話と矛盾するかもしれませんが、結構PENTAX6×7を最初に手に入れた時に、レンズの特性上、1メートル以上近づけなかったんですね。それが結構今のスタイルを、生んでるっていうのもあったりして。
O:はい。
H:ぼくは自分の子供をずっと撮ってたんですが、親が自分の子供を撮るっていうのも当たり前ではあるんですけども、どうしても客観的に見れないんすよね。愛らしいがゆえの視点で写真を撮ってしまう。気づいたら顔しか写ってない、でもそれを他人に百枚とか見せるのかっていうと、その、自分の家族や親類とかでなければやっぱり、難しいと思うんですよね。ふつうは知らない人の子供の写真にそんな興味はないと思うんです。だから、なんとなしに撮ってしまうと、なにかしらの意識とかコンセプトがない限りは、見る側はだんだんつらくなってくると思います。よっぽどその子が可愛くない限り(笑)。「そんなに見せられても」って多分なっちゃうと思うんですよね。ぼくは自分の子供を「可愛いでしょ、見て!」っていうことがやりたかったわけじゃなかったので、1メートル以上近づけないっていう距離感は、自分にとって一つの答えだったんですよね。それ以上近づけないから、逆にその距離感の中で子供達がどういうことをしてるかっていうのを表現するっていう発想になったんですよ。なので、それはカメラに使われてるっていう部類の話になるかもしれないんですけど。でもそれは、そのカメラを使うことで気づいたことですよね。
O:なるほど。でもそれが心地よかったというか、傑作を生むわけですね。
H:結果すごい自分にとっては良かった。その被写体との距離感を適度に保ちつつ、でも遠くはないっていう距離感を生めたのは、そういうのがあったからです。
O:うんうん。なんかぼくが、インスタでこの人をフォローしようかな、どうしようかな、ってなんとなく見てる時に、一番気にするのは「距離」なんですよ。その人とiPhoneの対象物の。で大概の人は近いんですよ。それはさっきも言ったけど、自分の身体的痛みなしに対象に近づけるからだけど、そこで、「引こう」って思う人が好きなんですね。たぶん自分自身もそうだと思うんですけど。人に自分を撮ってもらう時でさえ、相手がiPhoneを構えた瞬間に、「もう3歩、下がってくれる?」って注文出しちゃうタイプなんで。
H:(笑)。
O:その距離感が心地いいっていうのと、さっき話に出たデザイナー脳とか、編集脳がたぶん同時に働いてると思うんですよ。昔、編終了や先輩編集者にいやというほど言われたのは、「文字載っける余白残しておけ!」っていうことだったし。
H:(笑)。
O:「ここが空いてんのが嫌だと思うかも知んないけど、ここを空けとかなきゃデータが載せられないでしょ」みたいな。それが身についてるんでしょうね。あるいはそれがレコードジャケットになるんだったら「タイトル入れるスペースないじゃん」みたいな。
H:(笑)。逆にお伺いしたいのは、それって、編集者が使いやすい写真家だと思うんですある意味では。この人の写真はレイアウトしやすい、わかった撮り方してくれるっていうのと、いやいや、それはもう有無を言わさず、余白があろうがなかろうが、写真として力強いから、余白とかどうとかはいいんだっていうのと、編集者はどっちを求めているんですか?
O:駆け出しの頃は、自分にとって使いやすい写真を撮ってくれる人の方が組んでて、後で編集長に怒られなくていいなっていう感じだったんですけど(笑う)。まあ、何年もやってる内に、自分も『リラックス』で編集長をやることになって、やっぱり写真の力で人を捕まえないといけないっていう、そのことのほうが大事だなって思ったので、そこからキャプションを全て写真の外に出すっていう手法にしました。
H:おー。
O:(笑)写真を撮ってと頼んだんだから、その人が自由に撮ってなきゃ、多分、面白くないだろうと。写真が大事なので。そこに編集者の意図とか入れちゃダメなんだなって思った。編者者の意図はその枠の外に入れればいいっていうふうに思ったんですよ。そっから、写真の見方も変わりましたし、一緒に仕事をしたいと思う写真家の人たちも、全然違うタイプの人になりましたし。
H:でもやっぱり、第一線でやってる人っていうのは、それを両立してる人じゃないかなってぼくはは思っていて。
O:そうですね。
H:写真としてシンプルに力強いけど、レイアウトした時にもちゃんと使えるっていう、それが両立できてる人っていうのはやっぱり売れるんじゃないかって。そう思ってるんですが。
O:あとね、プロフェッショナルになったばかりの写真家、あるいは写真家になりたい人と話していて、職業写真、コマーシャル写真、コマーシャルフォトとか、まあファッションフォトもそこに入ると思うんですけど、そういうものを撮りたいのか、ストレートフォトというか、アートとしての写真みたいなのとどっちなんだという話題になる。シンディー・シャーマンとか杉本博司みたいになりたいのか、それともティム・ウォーカーとか、そういう人になりたいのか、それを両立できるのかっていうのを、みんなが悩むと思うんですけど。濱田君にはそういう悩みはあるんです? あるいはどっちになりたいとかあるんですか?
H:恐らくぼくはファインアートではないです。コンセプチャルな部分はあんまりないので、確固としたテーマを持って取り組んでそれだけを仕事にしてる、例えばプリント一枚売って50万、みたいなところにぼくはいないと思うし、それとコマーシャルの両立っていうのは一番難しいんではないかなと思ってて。いても数少ないと思うし。そういう人たちの傾向はやっぱりファインアートに振り切って芸術家として、写真というか、現代美術としての世界に生きている人が多いと思うんですよね。で、自分が今からそこに向かうかというと、そうではないなあと。僕はどちらかというと商業写真を撮るっていうスタンスで。自分のスタイルをいいと思ってもらって依頼してもらった仕事をしていきたいと思っていて。それができるのは、ファッションだったり、コマーシャルの仕事かなと思うんですね。ただ一方で、子どもをずっと撮ってきたのは、自分のキャリアを語る上で絶対外せないんです。あれはドキュメンタリーだったので。一切。作らないもの、ありのままを撮る。それって一見して分かりにくさもあると思っているんですね。もしかしたら、一枚だけじゃ伝わらないかもしれないし。その前後の文脈っていうものがあった上で成立する見方もあったりして。でもぼくは大衆に対してその手法とか撮り方を持ち込んだ時に、どういう風に見るかっていうのもやりたいんですよね。
O:なるほど。
H:わかりにくいものをわかりやすくしないといけない世界に持ち込んだ時に、いかに届けられるかっていうのに、ずっとチャレンジしているというか。で、今はそれをやってもいいというか、できる時代になったというか、そういうのを受け入れられる、みんな美意識みたいなのが備わってきているんじゃないかと思っているんですよ。要するに、日常の一枚でも広告に成り得るというか、今まではやっぱり広告といったらガチガチに作り込んで、こういうものを作りますっていうディレクターさんがいて、それに向かってみんな撮っていたんですけど。そういう目標がなくても好きなように撮ったものがひとつの答えになる。それが受け入れられる時代になってきたと思う。そんな世界をもっと自分で作っていきたいなと。今の僕の目標ですね。
– 以下略 –